まず大事なことをはっきり言うと、今の日本では「AIで作った画像を売った瞬間アウト」というわけではありません。
ただ、やり方によっては一気に危険側に転ぶこともあります。
この記事は法律の専門家の意見ではなく、実際にAI画像を使おうとした立場から調べてきた内容と、2025年時点で公表されている考え方を元にまとめたものです。
文化庁も「AIと著作権に関する考え方」を整理しており、AI生成物の扱いは今後も変わる可能性があるとしています。
「もう作っちゃったけど、これ売っていいのか分からない」という段階の人に向けて、違法リスクの高いパターンと、安全寄りの運用を、できるだけやさしく整理していきます。
AIで作ったイラストに著作権はあるのか
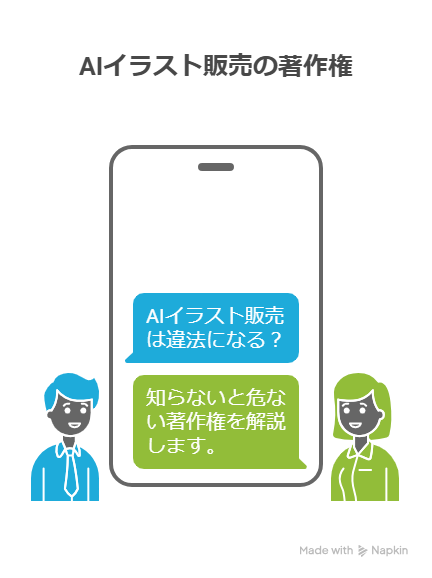
AI画像にいちばんよくある誤解は「AIが描いた絵には著作権がないんだから、自由に扱っていい」というものです。
ここには半分正しいところと、半分危ないところがあります。
日本の著作権法では、著作権は基本的に「人間が思想や感情を創作的に表現したもの」につきます。
AIそのものは法律上クリエイターとして扱われないので、AIが勝手に生成しただけの画像は、原則として著作物とはいえない、という整理が文化庁から示されています。
つまり、AIがボタン一発で作っただけの画像には「その画像自体の著作権者」がいない、という考え方がいまの基本ラインです。
ここだけを聞くと「じゃあ誰でも自由に使えるし、勝手に売っても問題ない」という気持ちになるかもしれませんが、そこで止まると危険です。
著作権がつかない場合でも、その画像が誰かの既存作品に似すぎていれば、別の形で「侵害だ」と言われる可能性があるからです。
さらに、AI画像でも人間がしっかり手を入れた場合は、状況が変わってきます。
たとえば、プロンプトを練り込み、何度も生成し直し、さらに構図や色を手作業で調整したり、別素材を合成したりして独自性を高めた場合は、人間の「創作的な寄与」があるとみなされ、その人自身が著作者と評価される余地があるという解説も増えています。
つまり「完全AI自動=ほぼ無権利で不安定」「AI+自分の編集=自分の著作物として主張できる余地あり」という二段構えで考えるとイメージしやすいです。
現場感で言うと、AIの下書きを“素材”にして、最後は人の作品に仕上げる、というイメージに近いです。
AIイラスト販売が違法寄りになるライン



AIで作ったイラストを販売するときに一番怖いのは、「これはアウト寄り」と判断されるケースに自分で気づけないことです。
AIは意図せず、既存の人気キャラや有名イラストレーターの絵柄にそっくりな画像を生成してしまうことがあります。
使う側としては「AIが勝手に出しただけ」でも、見る側には「それ、あの作品に似すぎじゃない?」と映ることがあります。
有名キャラや絵柄を狙った作品の販売
特に危険なのは、「特定の有名キャラクター」や「有名なイラストレーターの画風」を狙ってAIに描かせ、そのまま販売するパターンです。
ここで重要になるのが「依拠性」と「類似性」の2つです。
- 依拠性:元の作品を参考にしているかどうか
- 類似性:どの程度似ているか
この2つが揃うと、著作権侵害を主張される可能性が非常に高くなります。
たとえば「○○風」「○○っぽい」といったプロンプトで生成した場合、依拠性を疑われるリスクが上がります。
判断基準は“雰囲気”ではなく“構造”
「なんとなく似てる」ではセーフに見えても、実際の判断はもっと具体的です。
構図・色使い・線のクセ・衣装・ポーズなど、表現の本質部分がどこまで共通しているかで判断されます。
見た瞬間に「あのキャラ(あの絵師)だ」と連想されるレベルは、もう赤信号と考えましょう。
実在の人物やVTuberキャラの利用
次に危険なのは、実在の人物や公式キャラに似たAI画像を販売するケースです。
この場合は著作権ではなく、肖像権やパブリシティ権の侵害に発展するリスクがあります。
特に芸能人やVTuberなど、「キャラ性自体に商業的価値がある存在」に似せたAI画像は、運営や本人から直接「やめてください」と指摘されることが多いです。
ブランドやキャラクター性の“コピー”は危険
「誰かが長年育ててきたキャラクター性やブランド価値を、AIでコピーして売る」ほどリスクが高まります。
また、「オリジナル新作」として宣伝しておきながら、有名作家そっくりの絵柄を出すと炎上につながります。
法的な問題以前に信用を失うリスクの方が大きいです。
迷ったら“出さない”が安全策
「これはちょっと似てるかも」と感じた時点で、販売は避けた方が無難です。
AIが生み出す偶然の一致は、他人の目にはより強く「似て見える」ことが多いです。
迷ったら出さない──この判断が、長期的にはいちばん安全な防御になります。
AIイラスト販売が安全寄りになるライン
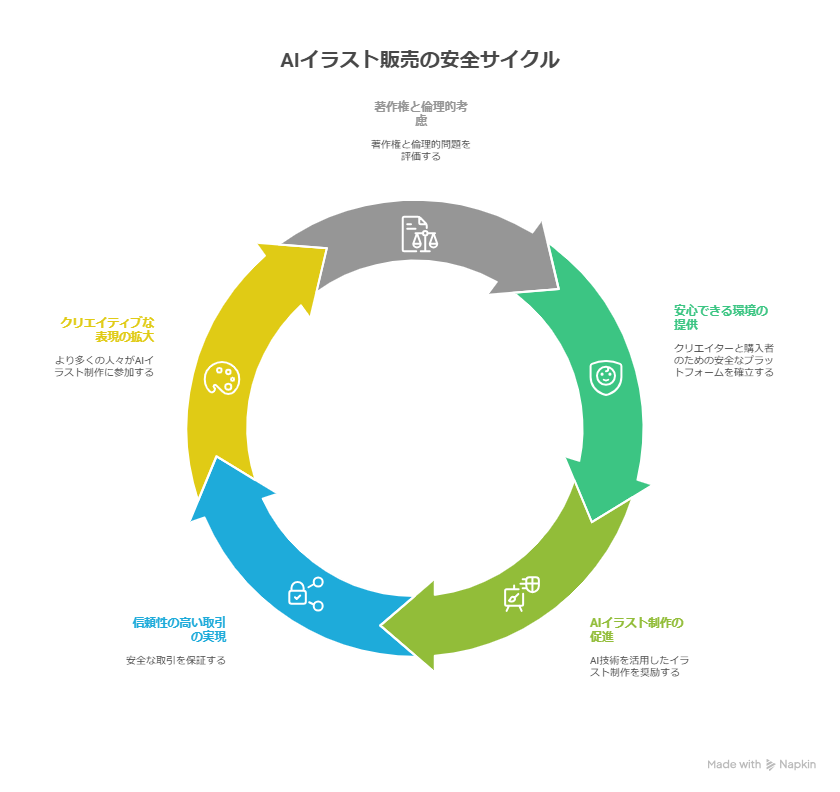
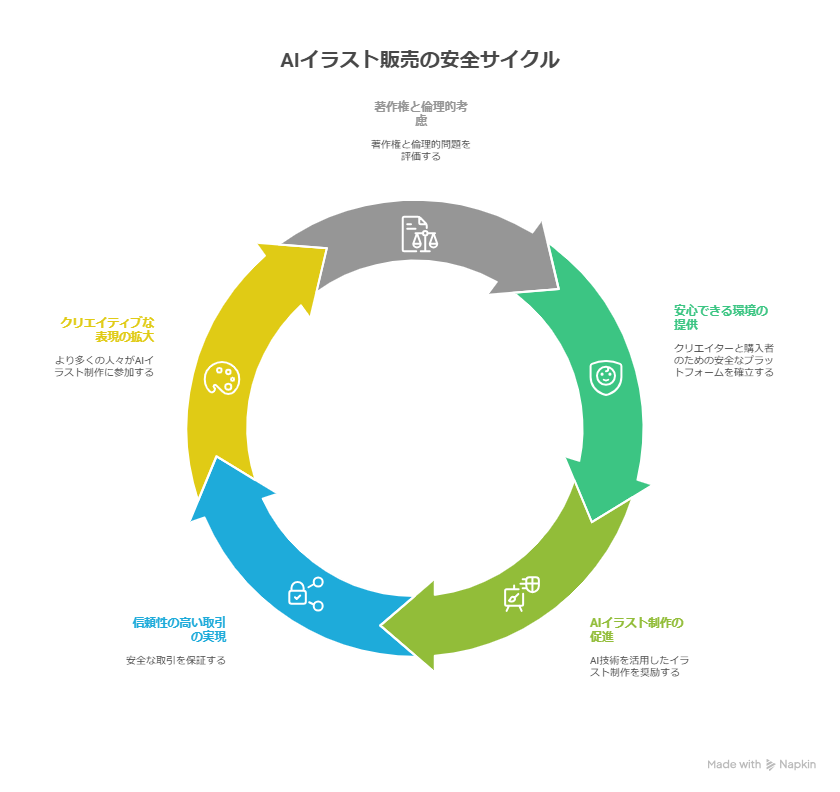
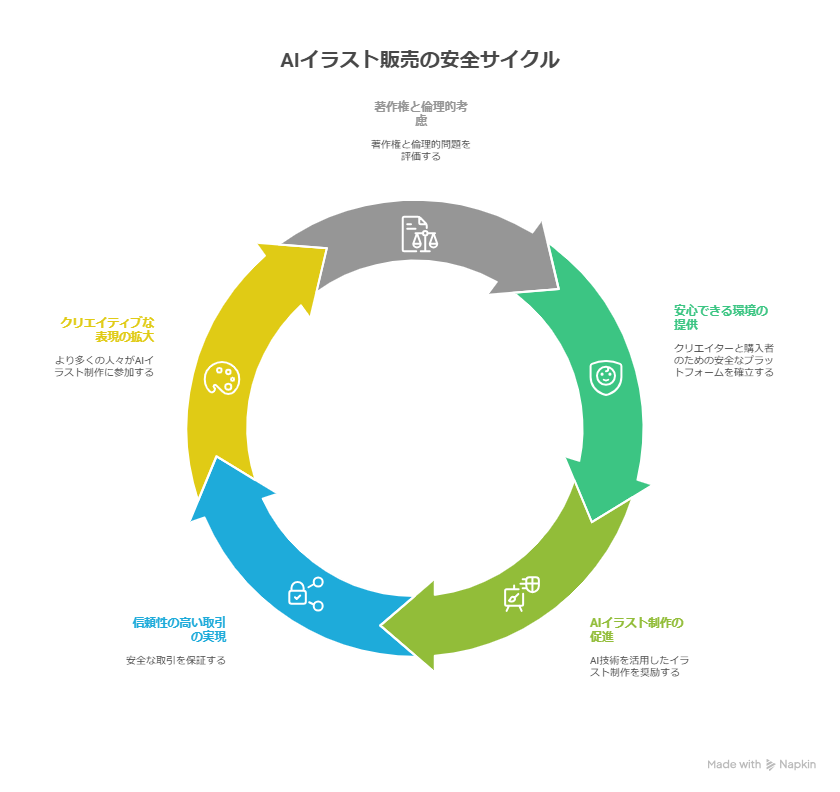
では、どんな販売なら安全寄りなのか。
大きく分けて3つのポイントがあります。
商用利用が許可されているツール・プランを使うこと
AIまかせにせず、人間の創作性を加えること
AI使用を明記して透明性を保つこと
商用利用可のツールを使う
AIツールの中には「無料プラン=商用NG」「有料プラン=商用OK」と分かれているものがあります。
MidjourneyやLeonardo AI、Canvaなどもプランによって商用範囲が異なります。
契約上OKな環境で作ることで、最初から「想定された範囲内の利用」として扱われ、リスクを下げられます。
自分の創作性を加える
生成した画像をそのまま売るのではなく、
- 背景とキャラを別生成して合成
- 色味やライティングを調整
- PhotoshopやCanvaで加筆・レイアウト変更
といった形で、自分の編集・判断が入ると「人間の創作性が加わった」とみなされやすくなります。
法的にも、心理的にも「自分の作品だ」と言いやすくなるラインです。
AI使用を明記して販売する
販売ページや商品説明欄に「AIを活用して制作しています」と記載しておくこと。
最近はBOOTHやSkebなどのプラットフォームでもAI作品に関するガイドラインが明確化されており、黙って出すことを最も嫌う傾向があります。
「AI+手作業で仕上げています」など制作プロセスを短く添えるだけでも、購入者に誠実さが伝わり、信用を守ることにつながります。
販売プラットフォーム側のルールは無視できない
ここは本当に現実的な話です。どれだけ自分の感覚で「これはオリジナル」と思っても、売る場所がNGといえばNGになります。
AIイラスト販売で使われやすいBOOTHでは、AI生成作品そのものは禁止ではありません。
ただし、既存作家に依拠したような模倣的な作品や、大量の類似画像スパム、修正が不十分なグレーな表現などは強く取り締まられています。
これは「法的にどうか」よりも前に、「そのマーケットの信用を守るために運営が判断して消す」という話です。
最近では、AIイラストを使ったショップ全体が検索結果から除外されるなど、作品単体ではなくアカウント単位で制限される例も出ています。
つまり、今の段階では「違法じゃなければOK」ではなく、「プラットフォームの許容ラインに合っているか」が現実の生存条件になってきています。
これは副業としてAIイラストを売りたい人にとってはかなり重要な視点です。
売る場所ごとにルールが異なるので、出品前にその最新の規約は必ず読むべきです。
「AIで作ったのに自分の作品として売るのは詐欺?」について
これはよく質問されるポイントです。AIで生成した画像を「完全に自分が描いた」として売るのは、トラブルの種になります。
買う側は「人間が描いた一点物」を期待していることもあるので、あとからバレると「だまされた」と受け取られることがあります。
極端な場合は、著作者名を偽ったとみなされるリスク(著作者名詐称)や、表示上の信用を損ねたとして問題視されることもあります。
逆に「AIベース+手作業で仕上げています」という形で、制作過程をはじめからオープンにしていると、大きな炎上になりにくいと感じます。
これは法律のテクニックというより、人としての信用の話に近いのですが、今はその信用がものすごく価値になっています。
トラブルを避けるために、最低限やっておきたいこと
AIイラスト販売を安全に続けたいなら、いくつかの行動を日常的に意識しておくと安心です。
少しの準備で、トラブルの多くは未然に防げます。
生成プロセスを記録しておく
どのAIツールを使い、どんなプロンプトを入力し、どこを手作業で修正したかを記録しておくことが大切です。
メモやスクリーンショットを残しておくと、後で「これは他人の作品に似ている」と指摘されたときに説明ができます。
自分を守る意味でも、制作過程を残しておくことは大きな防御になります。
似すぎたものは出さない判断をする
AIが生成した中には、意図せず有名なアニメや特定の作家の絵柄に似た画像が混ざることがあります。
そうしたものは販売ラインに乗せないようにしましょう。
売れそうに見えても出さない。
判断の基準は感情ではなく安全です。
少しでも迷ったら控える、その慎重さがトラブル回避につながります。
プラットフォーム規約を必ず読む
販売する前に、利用しているプラットフォームの規約を読むことは欠かせません。
特にBOOTHのような大手では、2023年からAI作品に関する方針を明確にし、2025年にはさらにルールが細かくなっています。
AI作品そのものは禁止されていませんが、特定作家の画風を模倣したものや、大量出品のような行為は非表示やアカウント停止の対象になる可能性があります。
販売前に一度は規約を確認する習慣をつけておくと安心です。
人間による加筆やアレンジを行う
AIが生成したままの画像よりも、手を加えた作品のほうが購入者からの印象が良く、プラットフォーム側にも独自性があると判断されやすくなります。
光の加減や配色の調整、構図の整理など、少しの工夫で作品の完成度は大きく変わります。
人の手が入ることで作品への責任感も生まれ、販売ページ全体の説得力も増します。
まとめ
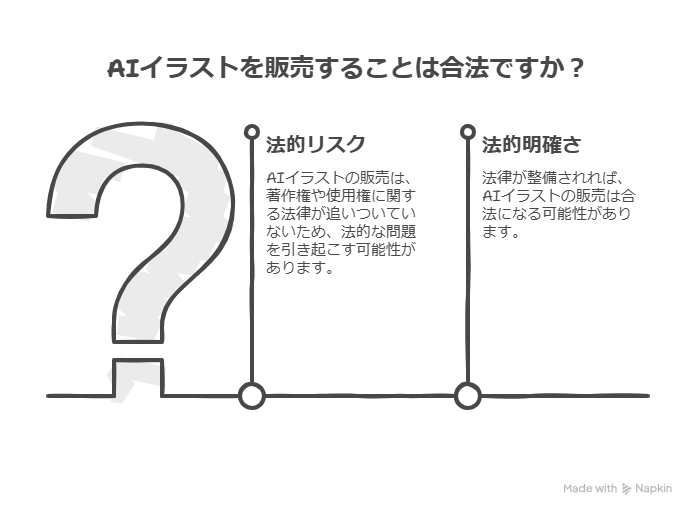
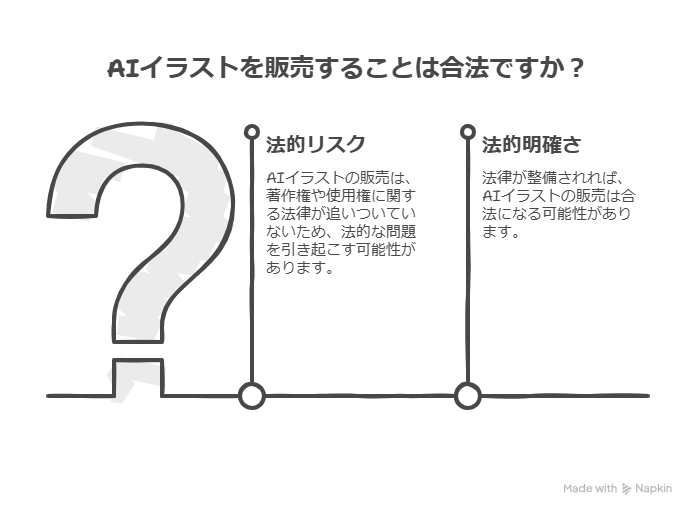
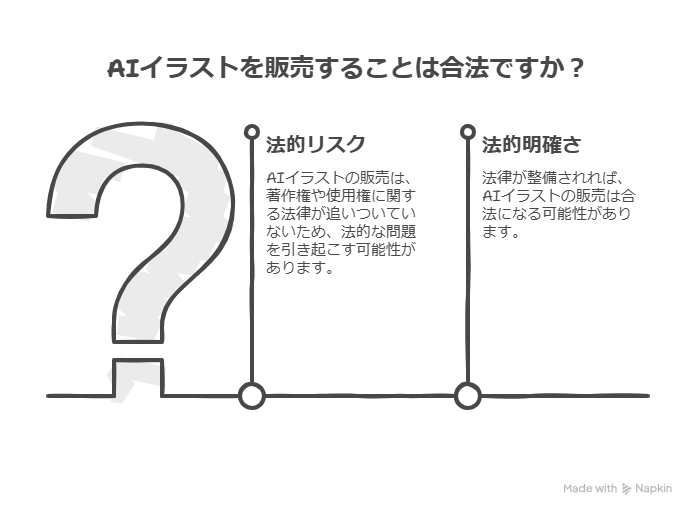
違法ラインは「丸パクリと混同させること」。
安全ラインは「自分の手で独自化して、正直に売ること」
AIイラスト販売は、完全に禁止されているわけではありません。
2025年の時点でも、BOOTHなどのマーケットではAI生成作品は出品可能です。
ただし、既存作家の画風に依存したコピー品や、ほぼ同じ画像を大量にばらまく行為は、強い規制対象になっています。
法的な観点でいうと、AIが自動生成した画像そのものには著作権が認められないことが多い、というのが現在の整理です。
ただし、誰かの著作物に似すぎた画像を公開・販売すれば、その時点で著作権侵害として問題になる可能性があります。
判断は「似ているか」「依拠しているか」という2点で決まります。
逆に、AIをベースにしつつ人間が構図・要素・色彩・テクスチャを調整して独自性を与えた作品は、利用者自身の創作として評価される余地があります。
そして、どこまでAIを使っているかをきちんと書いておくことで、購入者にもプラットフォームにも誠実な姿勢を示すことができます。
要するに、AIイラスト販売でいちばん大事なのは「黙ってそっくりさんを売らない」「AIで作ったことを隠さない」「自分の手で作品に責任を持つ」という3つです。
これは法律のすき間に逃げるためのテクニックというより、長く活動するための土台だと考えています。
今後、法改正や各プラットフォームのルールはさらに動くと予想されています。
文化庁も、AIと著作権の問題は継続して検討していくと明言しています。
この状況はしばらく続きます。
だからこそ、売る側も「まだはっきり決まっていないからこそ、自分は慎重にいく」という視点を持っておくと安心です。



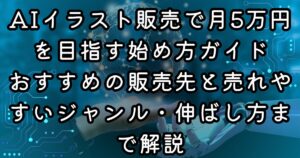





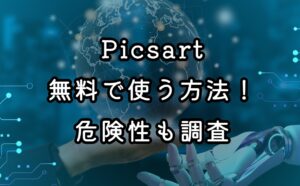
コメント