AIで画像やイラストを作れる時代になってから、「やってみたい」と思う人は一気に増えました。
ただ、実際に触ろうとすると最初に必ずつまずく場所があります。
どのツールを使えばいいのか分からない、無料で本当に使えるのか不安、商用利用は大丈夫なのか怖い。この3つです。
この記事では、AI画像生成をこれから始める初心者に向けて、安心して試すためのツール選びと、無料から収益化までのステップをまとめます。
内容はできるだけ実践的にしています。
この記事を読み進めながら実際に操作してみてください。
感覚的につかめるはずです。
AI画像生成ツールはどれを使えばいいのか



最初に決めたいのは「どのツールを使うか」ではなく「何を作りたいのか」です。
目的が決まると、必要なツールがほぼ自動的に決まります。
逆に、目的なしに何となくインストールすると、サブスク課金だけされて終わります。
これ、本当にあるあるです。
この章では、目的別にツールを選ぶ考え方を紹介します。
そのあとで、実際の使い方と無料でのコツをステップで解説します。
写真をきれいにしたい場合はPhotoDirector系
スマホで撮った写真を明るくしたい、背景だけ差し替えたい、人物の肌をきれいにしたい。
このタイプならPhotoDirectorのような「編集寄りのAI」が向きます。
PhotoDirectorは台湾のCyberLinkが提供している画像編集ソフトで、AIによる背景削除、顔補正、空の差し替えなどがワンタップでできるタイプです。
スマホアプリ版もあるので、パソコンなしでも使えます。
PhotoDirectorの魅力は、専門知識がいらないことです。
実際に触ってみると、やりたい操作のボタンがすでに用意されているので、撮った写真を「いい感じに整える」までがものすごく早いです。
これは制作ではなく“仕上げ”に強いタイプのツールと言えます。
ただ、PhotoDirectorには落とし穴もあります。
無料のように見えて、いろいろ触っているうちにPro機能に誘導されて、気づいたらトライアルから課金に移行していた、という流れが本当に起きやすいです。
広告も多めで、作業のテンポが途切れることも正直あります。
これは初心者にとってはストレスになるでしょう。
つまり、PhotoDirectorは「画像を整えたい人」や「人物写真・商品写真をきれいに見せたい人」に合います。
ただ、課金の仕組みと保存場所の扱いだけは最初に理解しておく必要があります。
後で詳しく触れます。
一からイラストや背景素材を生み出したい場合はAI生成系
描くのが得意じゃなくても、キャラクターや背景、ファンタジー風の世界観イラストを作りたいなら、いわゆる生成系ツールを使います。
Midjourney、Stable Diffusion、Leonardo AIなどがこのタイプです。
テキストで「こんな絵がほしい」と伝えると、そのイメージに近い画像をAIがゼロから出してくれます。
このタイプの強みは、オリジナル素材を大量に作れることです。
オリジナルの背景イラストをまとめて販売したり、アイコンや差し替え用の立ち絵を商品化したり、そういった収益化に向きます。
短時間で数を出せるので、物理的に“量”を用意できるのが強いところです。
ただし、生成系ツールは商用利用の条件がツールやプランによって違います。
無料プランだと商用利用がグレーなもの、あるいは禁止になっていることもあるので、販売前に規約を確認するのは必須です。
ここをスキップして販売してしまうと、一番もめるポイントになります。
まとめると、写真をきれいにしたいならPhotoDirectorのような編集系、イラストや背景を作りたいならMidjourneyやStable Diffusionのような生成系、というイメージを持つと迷いにくくなります。
このあと、実際の導入ステップを具体的に見ていきましょう。
初心者が最初にやるべきステップ



ここからは、完全に初めての人向けに、実際の導入から出力までのステップを並べていきます。
この順番でやれば、いきなり課金沼に落ちたり、保存した画像がどこに行ったか分からなくなったりしにくいはずです。
ステップ1:まず無料の範囲で触ってみる
いきなり有料プランに登録するのではなく、無料の範囲だけでどこまでできるのかをテストするのが最初の一歩です。
PhotoDirectorは無料版でもAI補正・背景削除などの基本操作を試せます。
ただし、いくつかの機能にはProマークがついていて、そのボタンを押すと突然「プレミアムプランへようこそ」という課金画面に飛ぶことがあります。
ここで焦って「1週間無料トライアル」を押してしまうと、自動的にサブスクが始まり、気づいたときには請求が発生していたという流れになることがあります。
これは本当に起きやすいので、まずは課金につながるボタンを押さなくても使える範囲だけを試します。
無料版のラインをはっきりさせておくことが、後のトラブルを防ぎます。
生成型のツールでも同じで、Midjourneyなどはアカウント登録後すぐに画像を作れますが、一定の利用回数を超えると有料プランへの移行が促されます。
課金前に、どのくらいの画質と再現性が出るかを確かめておくと、後から「思った感じと違った」という後悔が少なくなります。
無料で試す段階は、作品を完成させるよりも「操作に慣れる時間」だと思ってください。
ブログを書き始めた頃、まずは1記事目を完璧にしようとして固まってしまったことがありました。
結果的に、質より慣れのほうが大事だったんです。
AI画像も同じです。「どうやって指示を入れるとどう出るか」をつかんでください。
そこが最初のゴールです。
ステップ2:目的に合うモードだけを使う
PhotoDirectorを開くと、AIポートレート、アニメ化、背景削除、動画編集、コラージュなど、とにかく大量の機能が並んでいます。
全部を理解しようとすると一気に混乱します。
これは初心者が途中でやめてしまうパターンの典型です。
実際には、最初から全部使う必要はありません。
使うべきは一部だけでいいです。
もしSNSアイコン用のイラストを作りたいなら、テキストから画像を生成するモードだけを触れば十分です。
もしメルカリやハンドメイド商品の写真を整えたいなら、背景削除と明るさ補正だけで生活できます。
逆に、動画編集やエフェクトは、いま始めたばかりの段階ではまだいりません。
ツールは「全部の機能を使いこなす人」よりも「一つの機能を毎日使う人」のほうが成果を出しやすいです。
ブログでもいきなり100のSEOテクニックを覚えるより、1つのキーワードで検索意図に寄せるほうが確実に結果が出るのと同じです。
このステップでは、自分が何を作りたいのかをはっきりさせ、その目的に直結するボタンだけを使い続けてください。
それ以外は見なかったことにしてかまいません。
これは、迷いを減らすための小さな工夫です。
ステップ3:AIに与える指示文を工夫する
テキスト入力で画像を生成できるタイプのツール(PhotoDirectorのAI画像生成、Stable Diffusion系、Midjourney系など)は、どんな言葉を入れるかで結果がまるで変わります。
たとえば「海辺の風景」だけだと普通の海になりがちですが、「夕暮れの海辺に立つ木製の桟橋、オレンジ色の光、静かな雰囲気」というふうに、時間帯・素材・空気感まで入れると、一気に作品っぽい画像になります。
さらに「水彩イラスト風」や「アニメ風」「写真のような質感」などスタイル指定も入れると、狙いが明確になります。
これはブログのタイトルづくりと同じです。あいまいなタイトルではクリックされないのと同じで、あいまいな指示文では平凡な画像しか出てきません。
最初から完璧にやろうとしなくていいので、とにかく細かく書こうとするクセだけつけておくと、成長が速いです。
試してほしいのは、同じ内容で3パターンの言い回しを投げてみることです。
AIは日本語のニュアンスでも出力が変わるので、「静かな」「落ち着いた」「淡い」という似た言葉を入れ替えるだけで雰囲気が変わります。
この“微調整の遊び”を早めに経験しておくと、あとで販売用の素材を作るときに役立ちます。
ステップ4:保存場所と透かしの有無を確認する
生成した画像は、保存先を必ず把握しておきます。
PhotoDirectorの場合、ローカル保存とクラウド保存が分かれていて、どこに保存されたのか分からなくなることがあります。
実際に、保存したはずの写真が見当たらずにあせった経験があります。
あとからクラウド上に残っていることに気づいてホッとしたのですが、この手の焦りは一度は経験すると思います。
もう一つ大事なのが、無料版だと透かし(ウォーターマーク)が入ることがある点です。
ウォーターマークがあると、そのまま販売用素材にはしづらくなります。
逆に、SNSのヘッダー画像やブログのアイキャッチに使うぶんには、透かしが入っていても気にならないこともあります。
つまり、全用途でいきなり課金するのではなく、「これは公開用だから課金が必要」「これは練習だから無料でいい」という切り分けで考えると、ムダな支出を抑えやすいです。
保存まわりとウォーターマークは、初心者が軽視しがちなポイントですが、収益化を考えるなら避けて通れません。
ここを最初から意識しておくと、後で「この画像、売れないじゃん」という悲しいことにならずに済みます。
ステップ5:商用利用できるかをチェックする
ここは本当に重要です。
AIで作った画像を販売したい場合、商用利用の扱いを確認しないまま出品してしまうと、クレームの原因になります。
「このイラスト、自分で描いたんですか?」と質問されることもありますし、場合によっては「それ、別のサイトと似ていませんか」と指摘されることもあるからです。
PhotoDirectorの場合、有料プランでは生成した画像を商用利用してもいいとされる範囲があります。
ただし、無料版では制限があることもあります。
Midjourneyのようなツールも、プランによっては商用利用OKですが、無料プランだと不可ということもあります。
Stable Diffusionのようにオープンソースで自由度が高いツールでも、使っているモデルによっては著作権リスクが変わります。
つまり、「この画像は売っていいのか」「このキャラクターを依頼として受けていいのか」という判断は、ツールごとに答えが違うということです。
画像販売を副業として考えるなら、ここは読むしかありません。
プライバシーポリシーや利用規約を一度だけでも目を通すのは、本当に意味があります。
私がブログを始めたころ、著作権周りを軽く見ていて、画像引用のルールで後から冷や汗をかいたことがあります。
AI画像も、いまは誰でも作れるからこそ、こういう部分の意識で差がつきます。
丁寧な売り手は長く残る、というのはどのジャンルでも同じだと感じます。
無料で試しつつ、無駄に課金しないコツ



ここまででステップは一通りですが、もう少しだけ、無料ユーザー視点のコツもまとめておきます。
これを知っているだけでだいぶラクになります。
まず、無料期間のトライアルは一気に触るタイミングで使うのが安全です。
なんとなく登録して放置すると、自動的に課金が始まることがあります。
これはPhotoDirectorでも起きがちでした。
逆に、週末などまとまって触れる日にトライアルを開始して、必要な画像をまとめて作っておくと、かなり得をした気持ちになります。
要は「トライアルを本番として扱う」イメージです。
次に、広告まわりのストレスは見過ごさないでください。
無料版のAI画像アプリは広告を多く挟むことがあり、なかにはあまり安心できない広告が混じっている場合もあります。
編集したい画像より広告のほうが目に入ってイラッとすることもあります。
作業のテンポが切れると、継続する気力も落ちます。
そういうときは、より軽いアプリに一時的に乗り換えるのも手です。
自分に合うテンポのツールを見つけることは、意外と大事です。
そしてもうひとつ、画像が消える問題。
画像編集アプリは、ローカル保存とクラウド保存が分かれていたり、途中保存が自動だったりします。
保存場所の考え方はツールによって違います。大事な素材を作ったあと、必ず一度スマホ本体やPCへダウンロードしておくクセをつけておくと安心です。
旅行の写真がどこかに消えたまま見つからなくて冷や汗をかいたことがあるので、これは本気でおすすめします。
最初の一枚を作ったら何をすればいいのか
AI画像を作ったあと、その画像はどこで活躍できるのか。
これはモチベーションに関わる話なので、最後に触れておきます。
まず、SNSのアイコンやヘッダーに使うのは手っ取り早いです。
世界観のあるヘッダー画像は、プロフィールを見に来た人への印象に直結します。
次に、ブログのアイキャッチに使えば、クリック率が上がることがあります。
私のブログでも、AIで作ったビジュアルを使ったアイキャッチのほうが、地味なスクショだけのアイキャッチよりも明らかに反応が良かった時期がありました。
言葉より先に目に入るものは強いです。
さらに先の話になりますが、AIで作った背景イラストや透過済みの素材をまとめてパックにし、BOOTHやストック系サイトで販売することもできます。
イラスト一枚で大きく稼ぐというよりは、使いやすい素材をセットで並べていくイメージに近いです。
これは、ブログ記事を一つ売るのではなく、記事テンプレートをまとめて販売する感覚に近いと感じます。
今日からやるならこの順番



最後に、まだ何も触っていない状態の読者に向けて、今日やるべき行動を具体的にまとめます。
まず、PhotoDirectorのような編集系アプリか、いきなりイラストを作れる生成系ツールか、どちらが自分に近いかを決めます。
目的は「自分の写真を整えたい人」なのか「イラストを量産したい人」なのかで分かれます。
次に、選んだツールを無料の状態で起動して、一つだけ機能を触ってみます。
背景削除だけとか、テキストから画像生成だけとか、本当に一つで大丈夫です。
そこを深く触ったほうが上達が早いからです。
その後、保存と商用利用の条件を一度だけ確認します。
今後売る予定があるなら特にここは避けずにチェックしてください。
規約は面倒ですが、実はここが「収益化できるか」の境目です。
最後に、できあがった画像をどこかに使ってみてください。
SNSアイコンでも、ブログのアイキャッチでもいいので、目に見える場所に置いてみる。
これをやると、自分の作ったビジュアルが「消えるデータ」ではなく「誰かの目に触れる資産」に変わります。
AI画像生成ツールは、正しく選んで正しく使えば、初心者でも十分に使いこなせます。
最初の一枚さえ作ってしまえば、あとは改善していくだけです。
完璧を目指すより、まずは触ってみることから始めてみてください。
まとめ
AI画像生成ツールは「難しそう」と感じるかもしれませんが、実際は思っているよりずっと身近な存在です。
テキストでイメージを指示すればイラストが生まれ、ワンタップで背景を差し替え、写真をそれっぽく整えるところまで一気に進めてくれる時代になりました。
大事なのは、全部の機能を使いこなすことではなく、自分が何をしたいのかをはっきりさせることです。
写真をきれいに見せたいならPhotoDirectorのような編集系ツールが合いますし、オリジナルのキャラクターや背景を量産したいならMidjourneyやStable Diffusionのような生成系ツールが向いています。
この「自分はどっち側か」を決めるだけでも、無駄な課金や迷いはかなり減ります。
もう一つ、大事なポイントがあります。
それは、無料だからといって安心しきらないことです。
無料トライアルからの自動課金、広告の多さによる作業テンポの乱れ、保存先が分からなくなるトラブル、商用利用のルールが曖昧なまま販売してしまうリスク。
こういう細かいところでつまずく人は本当に多いです。
だからこそ、最初に確認しておくと後でラクになります。
この記事のステップをまとめると、まず無料で試す。
次に一つの機能だけを徹底的に触る。
仕上がった画像の保存先と透かしを確認する。
商用利用がOKかを読む。そして、その画像を実際にアイコンやブログに使ってみる。
この流れを踏むだけで、AI画像生成は「面白そう」から「ちゃんと使える」に変わります。
完璧な一枚から始める必要はありません。
むしろ最初の一枚は、お試しでいいんです。
そこから先が、あなただけの表現になります。






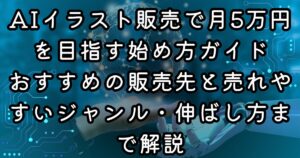



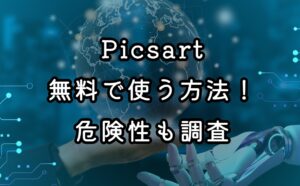
コメント